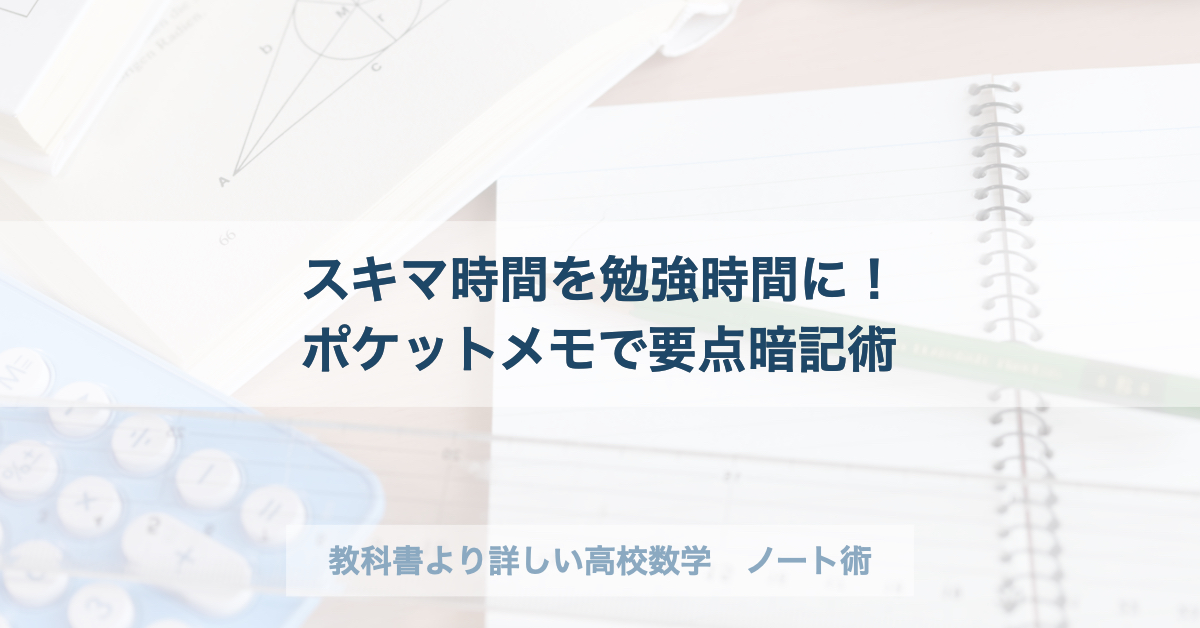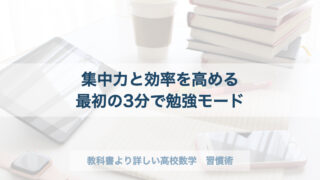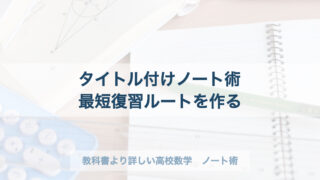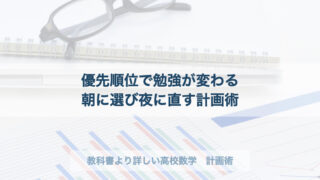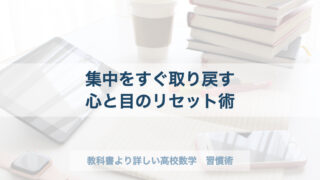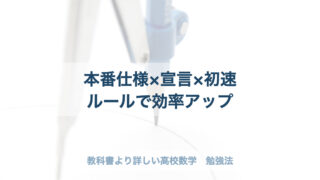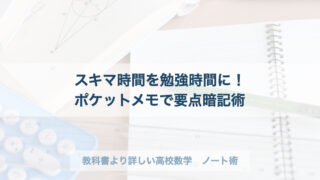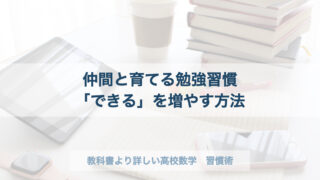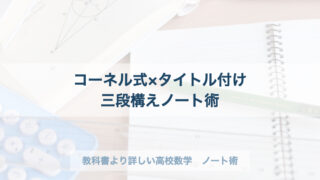メモは「全部書く」より「要点を押さえる」ほうが、理解も復習も速くなります。本記事では、授業中の要点抽出、授業直後の再構成、見返しルーティン、持ち歩きメモの活用まで、見返すだけで理解が深まるやり方を、今日から実践できる手順でまとめます。
授業中は“要点”だけを素早く拾う
- 重要語と結論を先に取る
- 強調・板書の変化に反応する
- 証拠や例は「→」で短く
授業で全部を書こうとすると、聞くことも理解も追いつきません。まずは「今日の結論」「定理や公式」「先生が強調した一文」を最優先でキーワード化。板書の色や枠線の変化は重要サインです。詳しい説明は「→例」「→証拠」と矢印で短く添える程度でOK。図や条件が多い問題は、図形や関係だけ写し、解説は授業後に再構成します。書き過ぎないからこそ、聞くと考えるに時間を回せます。
授業直後5分で“要点再構成”する
- 1行サマリーを必ず作る
- キーワード3つ+因果を一本線でつなぐ
- 次回の疑問を1つだけ書く
休み時間の最初の5分でメモを見返し、ページ上部に「1行サマリー」を書きます。次にキーワードを3つ選び、矢印で因果や手順を一本線につなぐと、後からの理解が飛躍的に速くなります。最後に「次回の疑問」を1つだけ残すと、復習の起点が明確に。ここで不足があれば、教科書の太字や例題を1つだけ追記して密度を上げます。
タイトル付けで“検索可能なメモ”にする
- 各ページに短い見出し
- 日付・単元・問題番号で手掛かり化
- ラベルで横断検索(例:微分/図形/語法)
見返しやすいメモは、開いた瞬間に中身がわかります。ページ最上部に短い見出しを付け、右肩に日付と単元、問題があれば番号も記録。複数科目を1冊に書く場合は、ページ先頭にラベルを付けて横断検索を可能にしましょう。例:「高2数Ⅱ|三角関数 合成」「英語|関係代名詞 that 制限用法」。タイトル化は、復習の最短経路を作る作業です。
就寝前と朝の“2回転”で定着させる
- 寝る前:1分×3ページの流し見
- 朝:1分セルフテスト(隠して言えるか)
- 週1回の総点検で間違いを潰す
記憶は間隔をあけた反復で定着します。就寝前は重要ページを1分×3ページだけ流し見。朝は同じページでキーワードを隠し、1分セルフテスト。「言えなかった語」を小さく追記します。週末はタイトルだけを一覧確認し、弱い単元にしるしを付けて翌週の復習キューに。量よりも“回す”ことが目的です。
持ち歩きメモでスキマ時間を回収する
- A6/B7サイズに“要点だけ”
- 1ページ=1テーマ、ページ番号管理
- 待ち時間15秒でもめくる
通学や待ち時間は最高の復習時間です。小さめのメモ帳に、公式や語彙、結論だけを1ページ1テーマで抜き出し、ページ番号を付けます。見出しとチェックボックスを置くと進捗が見える化。めくるリズムが付けば、1日合計5〜10分でも大きな差になります。スマホで写真メモを併用すると、図や板書の再確認もスムーズです。
よくある失敗と対策
- 書きすぎる → 重要語と結論だけ太字化。説明は矢印で一語に圧縮
- 見返さない → 就寝前1分と朝1分を“固定枠”化
- どこに何があるか迷う → ページタイトル化とラベル付けで検索可能に
まとめ
要点メモのコアは、授業中の「選択」と、授業後の「再構成」、そして毎日の「短時間ルーティン」。ページにタイトルを付け、就寝前と朝の2回転で回せば、メモは“見返すだけで理解が深まる”資産に変わります。今日から、1行サマリーと就寝前1分の流し見だけでも始めてみましょう。明日の理解スピードが確実に変わります。