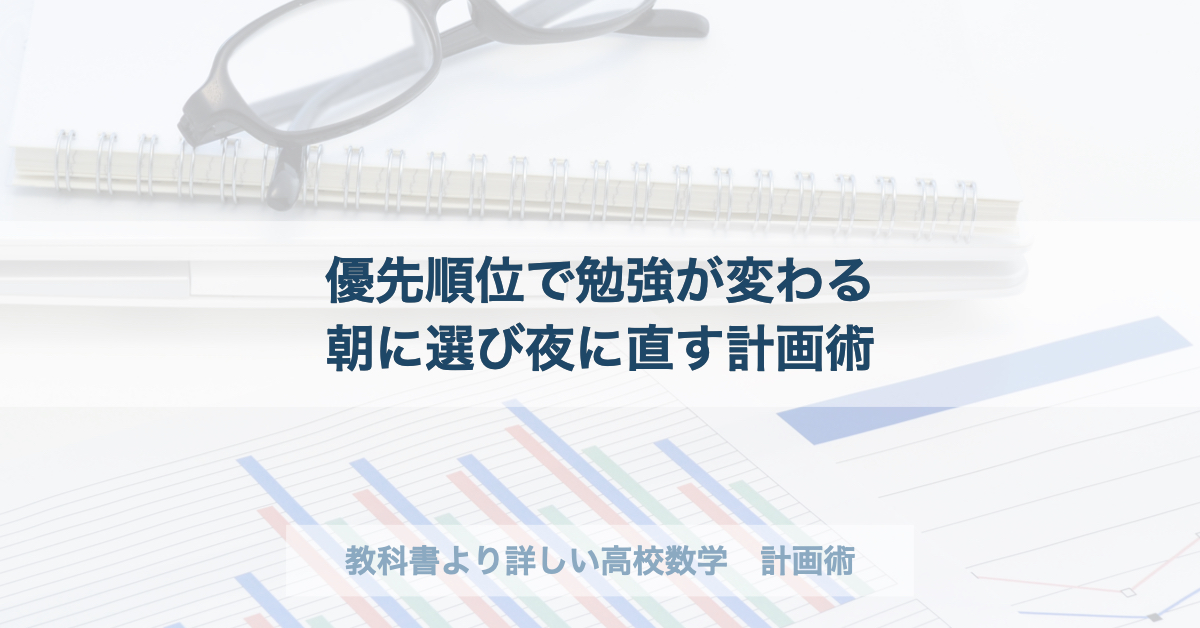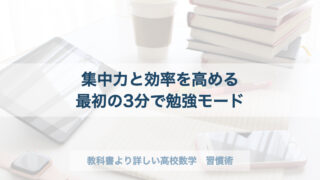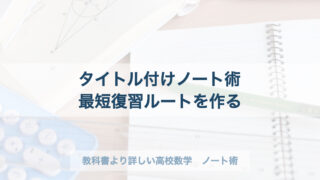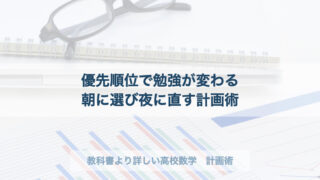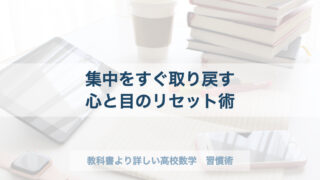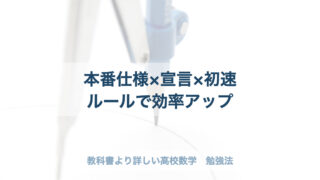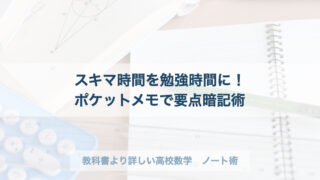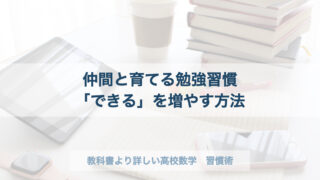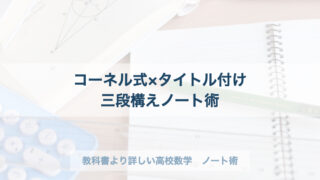テスト前ほどやることが増え、何から始めるか迷いやすくなります。大切なのは、朝に「やることを選ぶ」、夜に「やり方を少し直す」という流れを固定すること。この記事では、計画の土台になる「優先順位づけ」と、毎日を前に進める「セルフモニタリング」をセットで紹介します。完璧な計画より、回る仕組み。小さく進めて、こまめに直すのが最短ルートです。
優先順位づけの基本|今日やることを「重要×緊急」で仕分ける
- 最初の15分でToDoを四象限に粗く仕分けする
- 「非緊急だが重要」を核に、1日3タスクを時刻まで予約する
- 残りは「できたらやる」に退避して迷いを減らす
学習前に、紙やメモで今日の用事と学習タスクをすべて書き出し、重要度×緊急度で四つに分けます。テスト直前の演習や提出物は「緊急かつ重要」に置き、先に着手します。一方で、基礎の復習や単語の反復、弱点の克服などは「非緊急だが重要」。ここを一日の核として先に時間ブロック(開始時刻)を予約しておくと、緊急タスクに押されても学習の芯がぶれません。
「必ずやる」核は3つに限定し、開始時刻まで決めます。数学なら「例題→基本→典型応用」、英語なら「文法1項目→長文精読→単語40語」、日本史なら「通史流し→用語穴埋め→一問一答」のように、階段を作っておくと進みが安定します。核を3つに絞ることで進捗が数字で捉えやすくなり、翌日の調整も簡単になります。
セルフモニタリング術|毎日3分の客観視でブレを減らす
- 記録は「事実(時間・量・理解度)」と「解釈」を分ける
- 理解度はA(自力再現)B(ヒントあり)C(今は無理)の三段階
- 最後に「明日の修正案」を1行だけ書く
学習直後の3分を使って短く記録します。開始・終了と合計時間、解いた数や読んだページ数など「量」を残し、理解度をA/B/Cで判定。感想や要因は一言だけ添えます(眠気、難易度、環境など)。事実があるほど、次の一手が具体になります。
Bが多い日は「ヒントなし再現」を翌日に少量追加。Cが出たら前提インプットを10分差し戻します。集中が切れたなら時間帯を朝に移すか、学習環境からノイズを減らします。週1回は30分の「週間レビュー」を確保し、予定ではなく「できた量」で次週を組み直すと失速を防げます。
活用法|優先順位づけ×モニタリングを現実に落とし込む
- 朝は四象限→MIT3つを時刻まで予約。夜は3分ログ→修正1行
- 週末30分で「量・順番・難易度」を再配列。予備日を1〜2日確保
- 科目別に現実的な型を用意し、小さな締切で進捗を見える化
朝のルーティンでは、四象限で選び、核の3タスク(MIT)を時間ブロックに置きます。非緊急だが重要な学習を先に確保しておくと、短期の雑事に流されません。夜は3分ログで事実を残し、明日の修正を1行で決めるだけ。これだけで「決める→やる→直す」の循環が日単位で回り始めます。
週末は30分のミニレビューで、予定ではなく実績に合わせて再設計。量が過多なら分割、順番が悪ければ並べ替え、難易度が合わなければ一段階落とします。テスト期は予備日を1〜2日先に確保して、想定外の詰まりを吸収。
科目別の現実適用は、数学なら「例題をA判定(自力再現)で終えるまで短く反復。Bは翌日ミニテスト化」。英語は「時間制限演習」と「制限なし精読」を別日に分離して判定を明確に。理社は「通し→穴埋め→一問一答」で粒度を下げる流れを曜日固定に。さらに「単元ごとの小締切(例:金曜までに二次関数グラフをA判定)」を置くと、進捗が見え、修正も速くなります。
まとめ
計画の要は、選ぶ力と直す力です。朝に三つの核を時刻まで予約し、夜に三分で事実を記録して明日の一行を決める。この小さな循環が、学習の再現性を高めます。週に一度は「できた量」を基準に軽く組み直し、予備日と小さな締切で遅れを吸収してください。完璧を求めるより、回る仕組みを先につくること。今日から、朝の四象限と夜の三分ログを始めましょう。