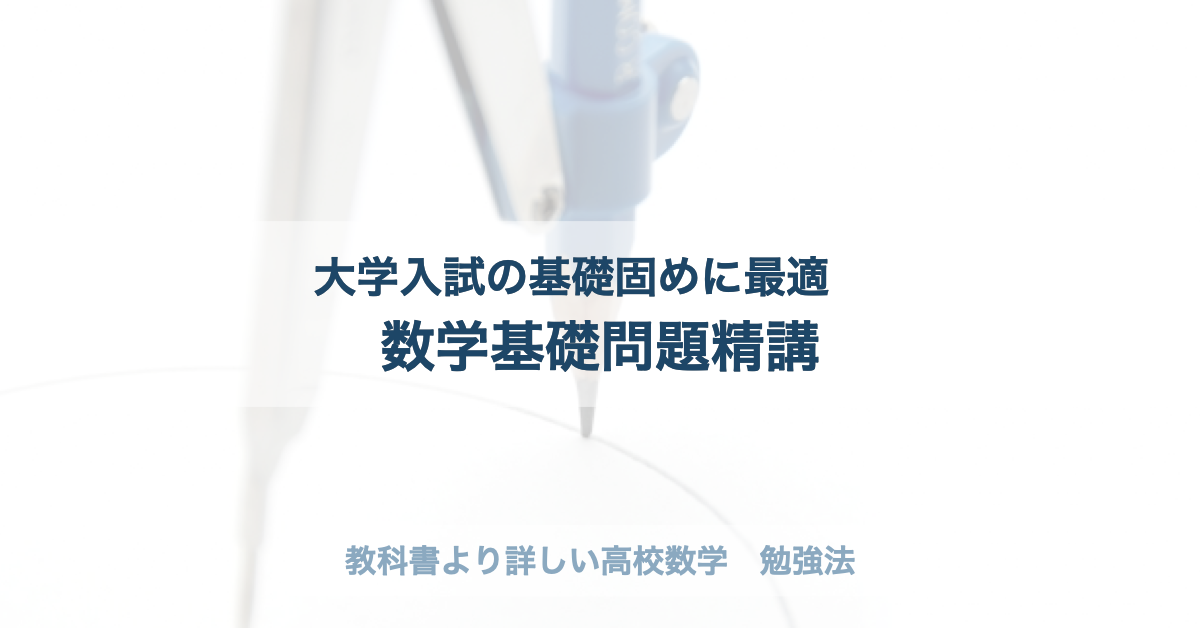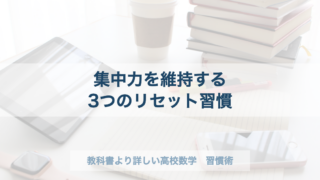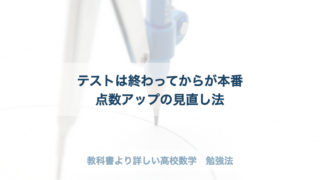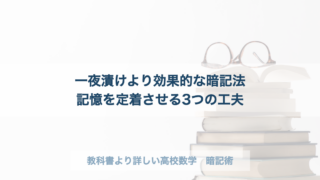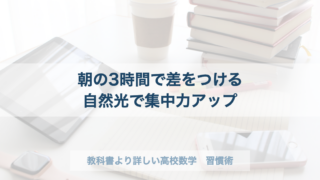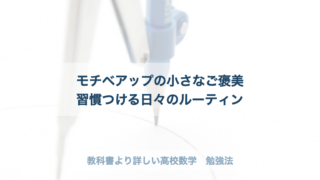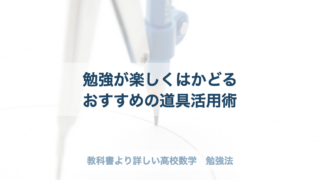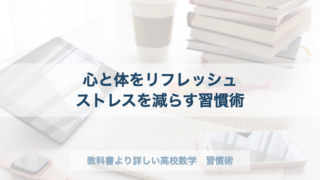旺文社の基礎問精講シリーズの紹介
数学の勉強で困っている高校生の皆さん、今回は大学入試に向けての基礎固めに最適な問題集「旺文社の基礎問精講シリーズ」をご紹介します。多くの受験生が利用しているこのシリーズについて、その特徴と効果的な使い方を詳しく解説します。
基礎問精講シリーズとは
「基礎問精講」という名前から、日常的な基礎問題集をイメージするかもしれませんが、実際には大学入試レベルの基礎を網羅した内容です。もし教科書レベルや定期テスト対策の問題集を探しているのであれば、同じ旺文社の「入門問題精講」シリーズを検討することをおすすめします。
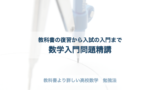
基礎問精講シリーズの対象
この問題集は以下のような学生に最適です。
• 教科書レベルの問題はほぼ理解している。
• 偏差値45〜50程度。
• 学校の学力テストや模試で点数が取れず、困っている。
• 大学入試の基礎固めをしたい。
さらに、大学入試まで時間はあるものの、チャートシリーズなどの分厚い参考書を使う時間がない学生にも向いています。
基礎問精講シリーズの構成
この問題集の構成は以下の通りです。
1. 例題:各ページの見開きに配置されています。
2. 精講:例題に対する公式や解法をまとめたものです。
3. 例題の解説:例題の解き方を詳しく説明しています。
4. 演習問題:例題の類題を解くことで理解を深めることができます。
基礎問精講シリーズの弱点
基礎問精講シリーズにはいくつかの弱点もあります。まず、例題の解説が不親切な点です。途中計算が省略されていることが多いため、教科書レベルの内容をしっかりと理解していることが前提となります。レベルが合っていないと感じた場合は、「入門問題精講」や教科書の内容に戻ることをおすすめします。
また、類題の解説が少なく、自力で復習するのが難しい場合もあります。わからない問題は学校や塾の先生に質問するようにしましょう。
基礎問精講シリーズの効果的な使い方
基礎問精講を効果的に使うためには、教科書レベルの問題がある程度解けるようになっていることが前提です。この問題集の進め方について、具体的な手順を紹介します。
■ 例題を3回解く
• 1回目:例題を解き、わからなければ精講と解説をよく読みます。
• 2回目:1回目からあまり時間を空けず(一週間以内)に解き直します。できなかった問題はしっかりと復習し、タイトル付きノート術を使って解法をまとめておきましょう。
• 3回目:さらに時間を空けて(数週間後)解きます。この時は単元別にまとめて解き、苦手な問題や忘れている問題がないかを確認します。ここで忘れている解法などは、タイトル付きノート術のチェックリストで確認するようにしましょう。


基礎問精講シリーズの注意点
基礎問精講シリーズの注意点として、数学Cの平面上のベクトルと空間ベクトルは数学ⅡBに収録されています。また、以前は基礎問精講シリーズに対応する「例題定着ノート」というものが販売されていましたが、現在のシリーズには対応していないため、購入時には注意が必要です。
まとめ
旺文社の基礎問精講シリーズは、大学入試の基礎固めに非常に有効な問題集です。ただし、例題の解説が不親切な部分もあるため、教科書レベルの内容をしっかりと理解していることが前提となります。効果的に活用するためには、例題を繰り返し解くことが重要です。自分に合った勉強法を見つけて、大学入試に向けてしっかりと準備を進めましょう。
このように、基礎問精講シリーズをうまく活用することで、大学入試に向けた確固たる基礎力を築くことができます。勉強の進め方を工夫し、弱点を克服しながら学習を進めていきましょう。